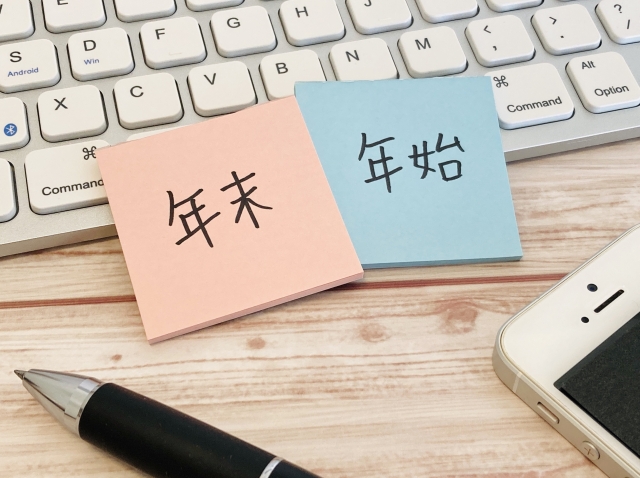年が明けて最初の出勤日、何気なく「仕事始めですね」と言ったあとに、「あれ?『始め』って『初め』じゃなかった?」と悩んだことはありませんか?
じつはこの2つ、意味も使い方も少し違うんです。ビジネスメールや挨拶で間違えてしまうと、ちょっと恥ずかしい思いをするかも。
本記事では、「仕事始め」と「仕事初め」の違いをわかりやすく解説し、ビジネスシーンでの適切な使い分けや言い換え例、英語表現までを一気にご紹介します!
「仕事始め」と「仕事初め」の違いとは?
「仕事始め」と「仕事初め」の意味や使い方、ビジネスにおける適切な選び方について詳しく解説します。誤用しやすい漢字の使い分けも丁寧に整理しています。
意味と使い方の違い
「仕事始め」は、年始における最初の勤務日を指すのが一般的です。
一方「仕事初め」は、“物事の始まり”という広い意味合いが含まれるため、年始に限らず新しい仕事をスタートする際にも使われることがあります。

“仕事初めのご挨拶を〜”ってメールに書いたんですが、これで合ってますか?

その使い方なら“仕事始め”のほうが自然だね。『初め』だと別の意味に取られるかもよ
どちらが正しい?漢字の使い方
“始め”は動作のスタートに対して使われ、“初め”は時期や順番、回数の最初に対して使われるのが基本的な使い分けです。たとえば「始める」「始まり」は“何かを動かし始める”という動作に重きがあり、「初めて」「初回」などの“初め”は出来事の順番や初体験を表すときに適しています。
このため、「仕事始め」は“年の初めに仕事を開始する”という行動に焦点を当てた言葉であり、より自然な日本語として定着しています。
一方で「仕事初め」は、“新しい仕事”に取り掛かるというニュアンスが込められており、必ずしも年始に限らないシーンで使われることがあります。
ビジネスシーンにおける使い分け
ビジネスメールや年賀状、公式な挨拶文では、「本年も仕事始めから気を引き締めて頑張ります」といったように“始め”を使うのが定番です。
この言葉には年始というタイミングを意識しつつ、前向きに仕事へ取り組む意思を込められるため、企業文化にもなじみやすい特徴があります。特に目上の方や社外の関係者に対して使う表現としては、“仕事始め”が無難で失礼がない印象を与えます。
混乱を避けるためのポイント
「どちらの表記も間違いではない」とは言え、TPOをしっかり考えて使い分けることが大切です。
たとえばビジネス文書や挨拶状では“仕事始め”を用いるほうが好まれますし、SNSなどカジュアルな発信では“仕事初め”と表現するのも許容範囲内です。とはいえ、統一感を意識するならば、社内外問わず「仕事始め」を基本とし、混乱や誤解を避けるように心がけると良いでしょう。
仕事始め・仕事初めの関係性
ここでは、両者の定義や位置づけを明確にし、年末年始の重要な節目としての意味や、挨拶表現での適切な使い分けについて紹介します。
仕事始めの定義とは?
“官公庁や企業で年明けに行う最初の業務開始日”が「仕事始め」です。
毎年1月4日前後がこれにあたります。
仕事初めの定義とは?
「仕事初め」はより広い意味を持ち、“その人にとって新しい仕事のスタート”を指す場合にも使われます。たとえば転職して初出勤の日などに「今日が私の仕事初めです」と言っても自然です。

じゃあ、新しいプロジェクトに取り組むときも“仕事初め”って言えるんですか?

うん、それはOK。でも年始の会社全体の動きに対しては“仕事始め”がいいね
年末年始における重要性
「仕事始め」は年始の節目として、社内の式典や神社への参拝行事などが行われることもあります。これは、1年の無事と繁栄を願う意味合いが込められており、日本ならではの伝統的な文化とも深く結びついています。
特に大企業や老舗企業では、社長の年頭挨拶や書き初めなどが行われ、社員全体が気持ちを新たにして業務をスタートさせる重要な節目となっています。
このような取り組みは、社内の士気向上やチームの結束力を高める効果もあるため、単なる出勤日とは一線を画す特別な日として扱われています。
挨拶における適切な使い方
年始の挨拶では「仕事始めを迎え、気持ちも新たに邁進してまいります」といった文面が定番です。より丁寧な印象を与えたい場合は、「本年もどうぞよろしくお願い申し上げます」といったフレーズを添えると良いでしょう。
一方で、「仕事初め」という表現は少しカジュアルで親しみのある響きがあるため、ブログやSNSの投稿、社内チャットなど、カジュアルな場面において使うと違和感がありません。用途によって適切な表現を選ぶことで、相手に与える印象もより良いものになります。
「仕事始め」と「仕事初め」の使い方
ビジネスメールやスピーチ、SNSなど、それぞれの場面にふさわしい表現例を交えて、自然に使える実例を解説します。
年始の挨拶に使える例文
- 「本日より仕事始めとなります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さまにとって実り多き一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます」
- 「新年の仕事始めにあたり、気持ちを新たに頑張ってまいります。初心を忘れず、日々精進してまいりますので、本年もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます」
ビジネスシーンでの具体例
- メールの冒頭:「仕事始めのご挨拶を申し上げます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます」
- 社内連絡:「1月4日(水)が当社の仕事始めとなります。全社員、通常どおり出勤のうえ朝礼を実施いたします」
- 挨拶スピーチ:「本日は仕事始めということで、気持ちを新たにスタートを切りましょう」
「仕事初めしごとぞめ」とは?
「しごとぞめ」という読み方は、実際には“仕事始め”を音読みと訓読みで崩した表現として使われることがあります。
SNSやカジュアルな場で親しみを込めて使われることもありますが、一般的な日本語としてはまだ広く認知されておらず、ビジネス文書や公式な場面では使用を避けるべき表現です。特にメールや文書で用いる際には、誤解を生む恐れがあるため注意が必要です。

“しごとぞめ”ってSNSで見たんですけど、アリですか?

気持ちはわかるけど、ビジネスでは使わない方が無難だね
「仕事始め」の英語表現
日本語での「仕事始め」を英語ではどう表現するのか、使いやすい例文と海外の文化的な違いについて詳しく紹介します。
英語での言い換え
「仕事始め」にあたる英語表現としては “the first workday of the year” や “first day back to work after the New Year holidays” が自然で、シチュエーションによって使い分けられます。
たとえば、社内でのカジュアルな会話なら “first day back” だけでも通じますし、よりフォーマルなビジネスメールでは “We wish you a productive first workday of the year” のような表現が使われることもあります。
また、“New Year’s return to work” というように、少し言い換えた表現も一部で見られますが、これはやや不自然な場合もあるため注意が必要です。
外国での文化的な違い
多くの欧米諸国では、日本のように仕事始めに特別な儀式を行う文化は少ないですが、メールや会話で “Happy New Year and welcome back to work!” のような挨拶が交わされるのが一般的です。
また、カレンダー上の区切りに対する意識が日本よりも柔軟であることもあり、年始の出勤初日があまり特別視されない傾向があります。
ただし、一部の企業では年初にキックオフミーティングを行ったり、部内で軽食を囲んで交流を深めたりと、カジュアルなイベントが設けられることもあります。国や業種によってもスタイルはさまざまで、文化の違いを踏まえたコミュニケーションが求められます。
2026年の仕事始めについて
2026年のカレンダーをもとに、いつから仕事始めになるのかを解説。また、時代とともに変化する働き方や仕事始めのスタイルにも触れています。
日本のカレンダーにおけるスタート
2026年の元日は木曜日です。企業によって就業開始日は異なりますが、カレンダーの並びから判断すると、多くの会社では1月5日(月)を仕事始めとする可能性が高いです。なお、1月4日が日曜である年には、休日明けの月曜日が業務開始日となることが一般的です。また、業種によっては1月6日以降にスタートするケースや、繁忙期を避けて早めに営業を開始する企業もあり、一律ではありません。サービス業や流通業などは年始から稼働しているところも多く、それぞれの事情に応じた判断がなされています。
働き方の変化と仕事始めの新スタイル
近年では、リモートワークやフレックスタイム制度の普及により、「全社員が一斉に出勤する」という従来の仕事始めのスタイルが大きく変化しています。オフィスに集まらず、各自が自宅からオンラインで参加する「リモート朝礼」や、「年始の挨拶メール」をもって新年の業務開始とする企業が増加しています。こうした柔軟な対応は、働き方改革やパンデミックを経た企業文化の変化を象徴しており、社員一人ひとりのライフスタイルに合わせたスタートが可能になってきています。また、業務開始日をフレックス対応にし、数日間の間に自由に出勤初日を設定できるようにしている企業もあるなど、より多様なスタイルが浸透しつつあります。

リモート勤務だと、出勤初日って実感わかないですね

そうだね。今は“物理的に出社”しなくても“心のスイッチ”を入れるのが大事かも
まとめ
「仕事始め」と「仕事初め」は似ているようでいて、実は使い方に微妙な違いがあります。特にビジネスシーンでは「仕事始め」がフォーマルで正確な表現として好まれます。一方、「仕事初め」はややカジュアルで個人的な表現に向いています。誤った使い方を避けるためには、意味と文脈の違いをしっかり理解しておくことが大切です。
年始の挨拶やメールをスマートに書き出して、良いスタートを切りましょう!